高齢者施設で生活相談員をしておりますわすれものです。
はじめに
「お世話する側が我慢するのが当たり前」
「家族だから、全部自分でやらなきゃ」
——そんな“介護のルール”、いつの間にか自分で作っていませんか?
実は、多くの介護者が「こうあるべき」という思い込みに縛られて、知らないうちに自分を追い込んでいます。
この記事では、介護がしんどくなる“勝手なルール”を見直し、心をラクにする5つの考え方をお伝えします。
「ちゃんとしなきゃ」がストレスのもと
介護をしていると、「失敗しちゃいけない」「完璧にやらなきゃ」と思いがちです。
しかし、介護は“人と人との関わり”。
天気や体調、相手の気分によって、昨日できたことが今日はできない——そんな日常が当たり前です。
完璧を目指すより、「今日はこれでよし」と思えること。
それが、介護を長く続けるコツです。
介護の現場でも「できることを、できる範囲で」が基本。
家族介護でも同じように、100点を目指す必要はありません。
“がんばりすぎない勇気”を持つことが、結果的に良いケアにつながります。

「私がやらなきゃ」は思い込み
「他の人には頼めない」「自分が一番わかっている」
——そう思う気持ちはとても自然です。
でも、それが続くと、介護疲れや孤独感が強まっていきます。
たとえば、
- デイサービスやショートステイを活用する
- ヘルパーさんに一部をお願いする
- 兄弟や親戚に分担をお願いする
こうした“頼る工夫”は、決して甘えではありません。
むしろ「続けられる介護」をつくるための大切な方法です。
介護はマラソンのようなもの。
一人で走り切るより、チームで支え合う方が、ずっと長く走れます。
「こうするのが正しい」は人によって違う
「食事は全部食べさせなきゃ」
「お風呂に毎日入れないと不潔」
——こうした“正しさ”も、時に自分を苦しめるルールになります。
実際には、体調や気分によって、その日の“ベスト”は変わります。
「今日は食べられなかったけど、水分は取れた」
「お風呂は無理だったけど、清拭できた」
それで十分なんです。
介護の目的は、“できたことの数”ではなく、お互いが安心して過ごせる時間をつくること。
「やらなきゃ」ではなく「できることを一緒にやろう」と考えるだけで、関係も穏やかになります。
自分の“ルール”に気づくための3つの質問
介護の中で、自分でも気づかない“思い込み”を抱えていることがあります。
次の3つを自分に問いかけてみてください。
- 「誰かに“こうするのが普通”と言われたから」やっていませんか?
- 「相手が喜ぶはず」と思い込んでいませんか?
- 「他の家族や周りの目」を気にしていませんか?
もし1つでも当てはまるなら、あなたの介護が“他人の基準”になっているかもしれません。
介護は“あなたと相手のペース”でいいのです。
まずは「自分のルール」に気づくこと。
そこから、少しずつ“本当の自分たちらしい介護”が見えてきます。
生活相談員からのひとこと
私が相談員として現場で関わってきた中でも、「勝手なルール」で疲れてしまう方は少なくありません。
たとえば、
「母が嫌がるのに、食事を全部食べさせなきゃと思っていた」
「父の介護を“嫁として当然”と感じていた」
でも、話してみると、本人も“そんなに頑張らなくていい”と思っていたというケースがよくあります。
介護は“相手のため”でありながら、あなたの笑顔も介護の一部です。
あなたが無理をして笑えなくなったら、それこそ相手もつらいのです。
どうか、「もう少し手を抜いてもいいんだ」と、自分を許してあげてください。

【まとめ】介護をラクにする合言葉:「まぁ、いっか」
介護に「正解」はありません。
あるのは、その人とあなたにとっての“ちょうどいい”介護です。
自分の中の“勝手なルール”に気づいたら、少しゆるめてみましょう。
「まぁ、いっか」と思えることで、心が軽くなり、介護の時間が少しやさしくなります。
あなたが笑顔でいられること——それが、介護の一番の力です。
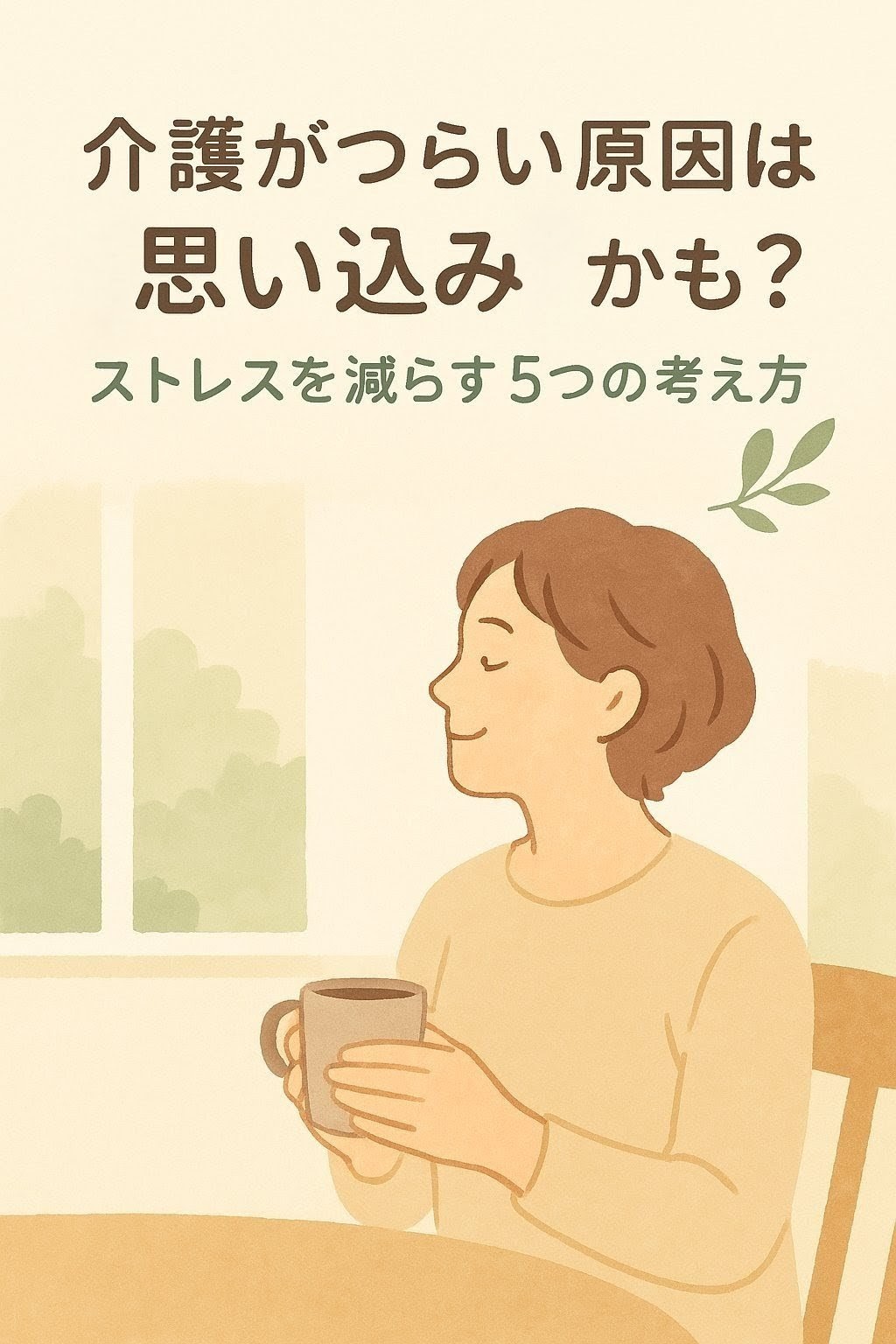


コメント