高齢者施設で生活相談員をしておりますわすれものです。
はじめに:認知症の人が見ている「世界」は、私たちとは少し違う
「お母さん、なんでそんなこと言うの?」
「さっき言ったでしょ!」
介護の現場や家庭で、そんなやりとりが繰り返されていませんか?
実は、認知症の人が見ている世界は、私たちの常識とはまったく違うルールで動いています。
この記事では、家族が知っておきたい「5つの視点」から、その世界をわかりやすく解説します。
理解することで、介護のつらさが少しラクになるはずです。

時間の感覚が変わる:本人にとって「今」は過去かもしれない
認知症になると、「今」と「昔」の区別があいまいになります。
たとえば80代のお母さんが、20代のころの夫を探している——そんな場面は珍しくありません。
本人の中では“今”がその時代のまま続いているため、「過去の世界で生きている」のです。
🟢家族にできること
- 否定せず、「そうなんだね」と受け入れる
- 写真や音楽など、昔の記憶を呼び起こすものを活用する
- 「今」を押しつけず、「その人の時間」に寄り添う
言葉の意味がうまくつながらない:話しても通じない理由
認知症が進むと、言葉を理解するスピードがゆっくりになります。
私たちの言葉が「かすれて聞こえる」ような感覚になることもあります。
本人に悪気はなく、脳が情報を処理するスピードが落ちているだけです。
「聞こえていない」のではなく、「理解に時間がかかっている」ことを忘れずに。
🟢家族にできること
- ゆっくり、短い言葉で話す
- 「どうしたの?」より「一緒にやろうか?」と行動を促す
- 表情や身ぶりで伝える
安心と不安の間を行ったり来たりしている:見えない不安との闘い
認知症の人は、“理由のない不安”を抱えて生きています。
「家が違う気がする」「財布がない」など、私たちには理解しづらい不安が突然わき上がることも。
その不安は、「混乱」ではなく“世界の見え方の違い”から生まれています。
🟢家族にできること
- 「大丈夫、ここはあなたの家だよ」と優しく声をかける
- 怒りや拒否の裏にある“不安”を見つめる
- 安心できる習慣(お茶、好きな椅子など)を大切にする
「できない」ではなく「やり方を忘れている」:思い出す力を信じて
服を着替えられない、料理ができない——
それは能力がなくなったのではなく、手順を思い出せないだけのことが多いです。
「昔は上手にできていたのに」と思うとつらいですが、
一緒にやることで、少しずつ“できる感覚”が戻ることもあります。
🟢家族にできること
- 手を添えて、「ここを持ってね」とサポートする
- 成功したらしっかり褒める
- 「できる部分」を見つけて伸ばす
感情は、最後まで残る:言葉がなくても心は通じる
記憶は薄れても、「うれしい」「悲しい」「安心した」という感情は、最後まで残ります。
たとえ言葉が通じなくても、心は感じ取っています。
だからこそ、家族の「笑顔」「声のトーン」「優しい手のぬくもり」が、何よりの支えになります。
家族が覚えておきたい3つの心構え
- 直そうとしない → 「できるようにする」より、「安心して過ごせる」が目標。
- 感情で受け止める → 理屈よりも「気持ちをわかってくれる」ことが大切。
- 自分を責めない → 介護は完璧じゃなくていい。「今日はこれでいいか」と思える日があるだけで十分です。

まとめ:認知症の世界を知ることは、やさしさの地図を持つこと
認知症の人が見ている世界を知ることは、「その人の立場に立つ力」を持つことです。
理解があるだけで、介護はぐっと穏やかになります。
「わかってあげたいけど、どうしていいかわからない」
そんなときこそ、今日紹介した5つの視点を思い出してください。
認知症の世界を少しのぞいてみる――それが、寄り添いの第一歩です。
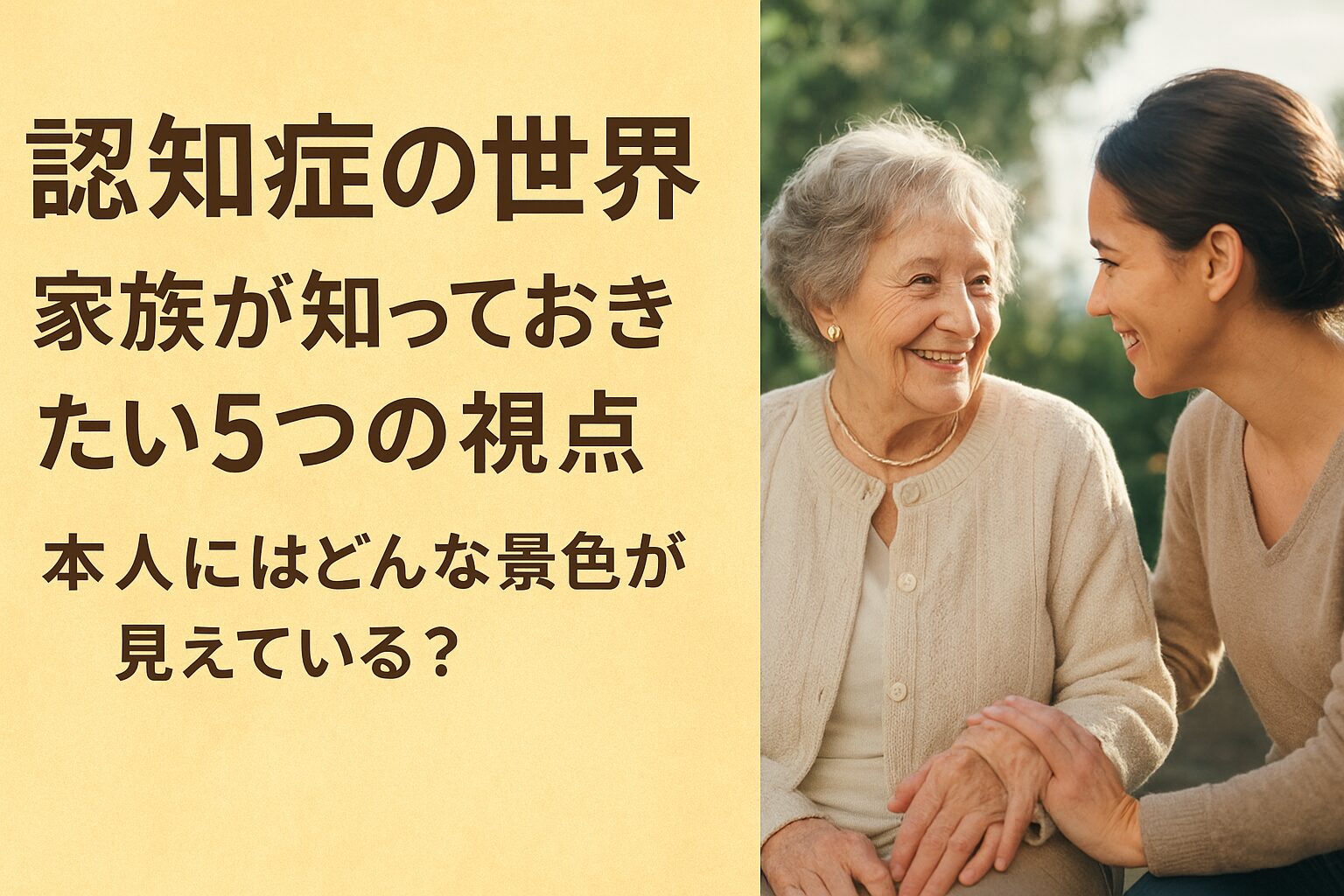


コメント