高齢者施設で生活相談員をしておりますわすれものです。
はじめに
「どうしてこんなことを言うんだろう」
「何度説明しても分かってもらえない…」
認知症の方との関わりで、そんなふうに悩んだことはありませんか?
実は、認知症の対応は“特別なスキル”が必要なものではなく、
私たちが日常で築いている人間関係ととてもよく似ています。
うまくいかないときこそ、「この人はどんな気持ちなんだろう」と
“心のやりとり”に目を向けてみると、関係が少しずつ変わっていくことがあります。
今回は、「認知症対応と人間関係は似ている」という視点から、
介護の場面で思い出してほしい3つのコツをお伝えします。
① 認知症対応は“人を理解する”ことから始まる
認知症の方も、私たちと同じように「分かってほしい」「安心したい」という気持ちをもっています。
たとえば、「帰る」と言うとき。
それは本当に“帰宅”を意味しているのではなく、
「落ち着かない」「不安」「ここは自分の居場所じゃない」といった気持ちの表れかもしれません。
人間関係でも同じですよね。
相手の言葉をそのまま受け取るのではなく、
「この人は今、どんな気持ちでそう言っているんだろう」と考えると、見え方が変わります。
認知症の方との関わりも、「言葉の裏にある気持ちを感じ取る」ことが、理解への第一歩です。
② 人間関係と同じ。“否定しない”ことが信頼をつくる
人間関係で一番つらいのは、「否定される」こと。
認知症の方も、それは同じです。
「そんなことないですよ」「違いますよ」と正しても、
その言葉が相手の“安心”を奪ってしまうことがあります。
たとえば、「お母さんが迎えに来る」と言われたとき。
「もうお母さんはいませんよ」と現実を伝えるよりも、
「お母さんに会いたいんですね」と気持ちに共感することで、
相手の心は落ち着いていくことが多いのです。
信頼は、正しさではなく“受け止める力”から生まれます。
人間関係の基本と同じように、認知症対応でも「否定しない」姿勢が何より大切です。
③ 感情に寄り添う。“言葉より心”でつながる
認知症の方は、言葉の意味よりも表情や声のトーンを感じ取っています。
だからこそ、どんな言葉を選ぶかよりも、どんな気持ちで話すかが大切です。
たとえ短い会話でも、
「笑顔で」「やさしい声で」「相手の目線に合わせて」関わるだけで、
相手の反応がやわらかくなることがあります。
反対に、焦りやイライラをそのまま出してしまうと、
不思議なほど相手にもその感情が伝わってしまいます。
そんなときは、まず深呼吸をひとつ。
「この人も不安なんだ」「うまくいかないのは私のせいじゃない」と
自分の気持ちを落ち着けてから、ゆっくり声をかけてみましょう。
④ うまくいかないときは、自分を責めないで
どれだけ丁寧に関わっても、うまくいかない日もあります。
それはあなたが悪いのではなく、**人間関係と同じで“相性”や“タイミング”**があるだけのことです。
疲れたときは、無理せず距離をとっても大丈夫。
誰かに話を聞いてもらうだけでも、心が軽くなります。
「完璧な対応」なんて、介護の世界にはありません。
今日も笑顔で挨拶できたなら、それで十分です。
自分を責めるより、「よく頑張ったな」と自分をねぎらってあげましょう。
⑤ まとめ:認知症対応は、心と心のコミュニケーション
認知症対応は、難しい専門技術ではなく、
“人と人との関わり”そのものです。
相手の気持ちを受け止めること。
言葉よりも表情や声で安心を伝えること。
そして、うまくいかない日があっても、自分を責めないこと。
それらはすべて、人間関係の中でも大切なことですよね。
認知症の方との関わりを通して、
「人を思いやる」という人間らしい優しさを、
改めて感じるきっかけになればうれしいです。

こちらのブログも良かったらどうぞ


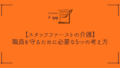

コメント