高齢者施設で生活相談員をしておりますわすれものです。
失語症とは?脳の障害で「ことばの理解・表現」が難しくなる症状
失語症(しつごしょう)は、脳の言語を司る部分に障害が起きることで、話す・聞く・読む・書く力が低下する状態をいいます。
目や耳には問題がないのに、「言葉として理解・表現する力」だけがうまく働かなくなるのが特徴です。
日本では、脳卒中(脳梗塞・脳出血)後の後遺症として発症する方が多く、高齢者の介護現場でもよく見られます。
適切なリハビリを行うことで、少しずつ回復していくケースも少なくありません。
⚙️ 失語症の主な原因
失語症を引き起こす主な原因は以下の通りです。
- 脳梗塞
- 脳出血
- 外傷性脳損傷(事故など)
- 脳腫瘍
- 脳炎
これらにより、脳の言語中枢(ブローカ野・ウェルニッケ野など)が損傷を受けると、言葉を理解する力や発する力が低下します。
🗣️ 失語症の3つのタイプと特徴
感覚性失語(ウェルニッケ失語)
- 言葉は流暢に出るが、内容がちぐはぐになりやすい
- 他人の話の意味を理解しにくい
- 読んでも「内容がわからない」状態
👉 外国語の文章を見ているような感覚に近いです。
運動性失語(ブローカ失語)
- 理解はできるが、言葉が出てこない・話すのが遅い
- 話す途中で止まる、言葉が途切れる
- 書くことにも困難を伴うことがある
👉 頭では分かっていても、声に出せないもどかしさが特徴です。
失読失書(読み書き障害)
- 文字が「記号のように」見える
- 読み書きの両方が難しい
- 「あ」と「お」など、似た文字の区別がつかないことも
👉 目には見えているのに、脳が文字情報を認識できない状態です。
👀 失語症の方にとって、文字はどう見えているの?
失語症は視力の問題ではなく、脳の中で言葉を処理する仕組みに問題が起きているため、
「文字が見えても意味がわからない」ことがあります。
たとえば「りんご」という文字を見ても、🍎 のイメージが浮かばない状態です。
そのため、「読めていると思っても理解していない」ことがあります。
📌対応のポイントは、「理解しやすい工夫」をすることです。
写真・イラスト・ジェスチャーなどを併用すると、より伝わりやすくなります。
💪 リハビリで回復する可能性もある
失語症のリハビリは、**言語聴覚士(ST)**によって行われます。
代表的な訓練内容には、次のようなものがあります。
- 絵カードや写真を使った理解練習
- 言葉の復唱・発音トレーニング
- 書字訓練(漢字・ひらがなの練習)
- ジェスチャー・アプリを使ったコミュニケーション支援
リハビリの効果は個人差がありますが、早期に始め、継続することで改善が期待できます。
🌷 家族ができる「5つの接し方」のコツ
失語症の方と接するときは、焦らず、ゆっくり、わかりやすくが基本です。
次の5つを意識するだけで、コミュニケーションがぐっと楽になります。
ゆっくり・はっきり話す
→ 一文を短くし、ゆっくり伝えましょう。
一度に多く話さない
→ 情報量が多いと混乱しやすくなります。必要なことだけを簡潔に。
ジェスチャーや写真を使う
→ 言葉だけでなく、目で見てわかる情報を添えると伝わりやすいです。
筆談やアプリも活用する
→ スマホのメモやイラストアプリも、立派なコミュニケーション手段です。
「できた!」を一緒に喜ぶ
→ 成功体験が自信につながり、リハビリのモチベーションにもなります。
💬 まとめ:言葉が出なくても、心はつながっている
失語症は「ことばの障がい」ですが、気持ちまで伝わらなくなるわけではありません。
言葉が出にくくても、表情・しぐさ・目の動きなど、コミュニケーションの形はたくさんあります。
家族が「伝える工夫」を続けることで、失語症の方の世界は少しずつ広がっていきます。
焦らず、一緒に“わかり合える瞬間”を積み重ねていきましょう。

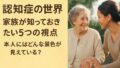

コメント