高齢者施設で相談員をしておりますわすれものです。
先日、利用者の内出血の件で報告書が提出されました。利用者(高齢者)は、皮膚が極端に薄く、薬の副作用や乾燥し弾力性も失っていることから、ちょっとぶつけたたげて、内出血しやすい傾向があります。
ご自身で動かれる方なら
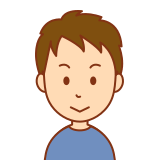
どこかでぶつけられたのかな?
と、利用者へ確認しますが、寝たきりの方は出来る箇所にもよりますが、概ね介助中に出来たものか、拘縮による圧迫で出来るものが多いです。
しかし、時には
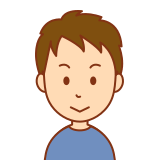
こんなところに?どうやって??
と思うケースもあります。スタッフの不注意から出来たと思われる内出血は、極力作らないようにしないといけません。
内出血が起きやすい理由を理解しよう
高齢者の皮膚や血管は年齢とともに変化します。
- 皮膚の薄さ・乾燥
加齢により皮下脂肪や水分が減少し、皮膚は薄く乾燥しやすくなります。 - 血管のもろさ
動脈硬化や血管壁の老化で、ちょっとした刺激でも血管が破れやすくなります。 - 薬の影響
抗血小板薬・抗凝固薬など、血液をサラサラにする薬を服用している方は特に出血が止まりにくくなります。 - 栄養不足や生活習慣
ビタミンCやK、タンパク質不足も血管や皮膚の健康に影響します。
まずは「なぜ起きるのか」を理解し、「仕方ないこともあるが、対策で減らせる」という視点を持つことが大切です。
内出血を作らないための対策
上からの落下物
地震の際、臥床中の利用者に、物が落ちてこないように対策する必要があります。何かが落ちてきた場合は、内出血だけでなく大きな怪我に繋がりかねないですが、ベッド上部に何も置かない事が一番です。引き出し扉がある場合は、簡単に開かないように、ドアストッパー等付けていると安心です。
オムツ交換時や体交時
側臥位にポジションニングを取る際、拘縮等で難しく、勢い余って柵やサイドレールにぶつけてしまう事があります。予防の為に、サイドレールカバーやクッションを置いて、身体が直接当たらないようにする事が必要です。身体の向きを変えた際、どの位置にあるか目測を誤らないことも大切です。
車椅子
移乗時に、車椅子のフットレストに当たって出来る内出血は多いです。フットレストカバーの装着をするとともに、今は標準装備になりつつありますが、フットレストが左右に開くタイプを選ぶのが、予防になります。また、利用者には厚手の靴下やレッグウォーマーを着用して頂くと、さらに効果があると思います。皮膚が弱い方は、腕にもアームウォーマーをつけておくと良いでしょう。
グッズの活用でさらに安心
- 手すり・家具用コーナーガード
シリコンやクッション性のある素材でぶつかっても安心。 - スリッパ・室内シューズ
滑りにくい素材を選びましょう。 - 長袖・長ズボン
肌の露出を減らすだけでも打撲や擦過傷を防ぎやすいです。
栄養面からのサポート
環境だけでなく、内側からのケアも大切です。
| 栄養素 | 働き | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| ビタミンC | 血管や皮膚のコラーゲン生成 | みかん、ブロッコリー、パプリカ |
| ビタミンK | 血液の止まりを助ける | 納豆、ほうれん草、小松菜 |
| タンパク質 | 血管や筋肉の材料 | 卵、魚、鶏肉、豆腐 |
栄養バランスを意識することで、血管や皮膚の強化につながります。
起きてしまった時の対応
内出血はすぐに目立たなくても、あとから紫色になって出てくることがあります。
- まずは冷やす(腫れや痛みがある時)
- 範囲・形・発生日時を記録
- 異常な腫れ・痛み・出血があれば医療機関へ
- 家族や関係者に経過を共有し、再発防止策を検討
記録を残すことで「どこで何があったか」を振り返りやすくなり、トラブル防止にもなります。
ケーススタディ
「利用者さんがベッド柵に軽く腕をぶつけただけで、大きな青あざになってしまった」
このような経験をした介護スタッフは少なくありません。
このケースでは、柵に厚手のカバーを追加しただけで内出血の発生率が減少しました。
また、本人には長袖を着用してもらい、皮膚を保護することで予防効果がさらに高まりました。
まとめ
高齢者の内出血は避けられない部分もありますが、「知っておく」「工夫する」ことで確実に減らせます。
- 環境整備で衝撃を減らす
- 栄養・服薬の知識を持つ
- 記録・対応を徹底して家族やスタッフ間で共有する
こうした小さな積み重ねが、ご本人の安全と家族の安心につながります。
また、ちょっとの内出血でも、「虐待をしているのでは?」と、家族とトラブルに発展するケースもあります。内出血を防ぐ為の環境整備と、出来た場合の説明をしっかり行う事が、家族の信頼感に繋がりまし、何よりも利用者の生活の安全の保証になります。
力任せの介護で、利用者に内出血を作ってしまう事だけは、プロとして避けたいものです。



コメント