「やさしくしているはずなのに、なぜかうまくいかない」そんな経験はありませんか?
実はその“やさしさ”、ちょっとズレているかもしれません。
はじめに
介護施設で生活相談員をしておりますわすれものです。
介護現場ではもちろん、介護をされている方のほとんどは、
「やさしくしてあげよう」
「支えてあげよう」
「力になりたい」
という思いがあるはずです。でも、その“やさしさ”が、時に相手の気持ちを置き去りにしてしまうことがあるんです。
「全部やってあげること」が本当のやさしさ?
あるご家族の話です。
認知症のお母さんが、食事をこぼすのを見て、
「もう私が食べさせるから」
と娘さんが全部口に運んでいました。一見、やさしく見えるその行動。
でもお母さんは、どこか寂しそうな顔…。実は、
「自分で食べたい」
「できることは自分でやりたい」
という思いが、まだちゃんと残っているのです。
「見守るやさしさ」もある
やさしさって、「してあげること」だけじゃありません。
「できることは見守る」
「失敗しても寄り添う」
これも立派なやさしさです。たとえば、歩くのが少し不安な親御さんに対して、すぐに手を引っ張ってしまうことがあります。
でも、「そっと隣を歩いて見守る」だけで、本人は自信を持って一歩踏み出せることもあるんです。
ご利用者から頼まれたら断れない
介護施設でよくある風景。ご利用者から
「手伝って。」
と言われると、関係性を悪化させないため介護スタッフが仕方なく手伝う事も少なくありません。
もし、【自分の為に】とスタッフが断ってしまえば、
『あの人、何もしてくれん』
『あの人は、冷たい人』
ご利用者は、そう感じ取ってしまうかも…。
「手伝って」という背景には
- 不安を和らげてほしい
- 関わりを持ちたい
- 孤独を感じている
- 自分の存在を認めてほしい
というニーズが隠されている事があります。自立支援は大切ですが、その方の状態や気持ちに合わせたバランスが重要です。
「自分の為に」という言葉には温かい意図があっても、受け取る側にとっては冷たく感じられることがあります。
言葉の選び方や伝え方を工夫し、相手の気持ちに寄り添いながら自立を支援していくことが大切です。
介護の現場では、「共に歩む」姿勢が信頼関係を築く鍵となるでしょう。
【安全の為】という目的で
本来ならご利用者にして頂くところを、安全の為に全てスタッフが介助してしまうケースも見受けられます。
「自分で食べると早食いで危ないので手伝う」
「杖歩行で転倒したら怪我するので、車椅子を使用する」
「トイレにきちんと座ることが難しいので、オムツを装着する」
安全という目的でスタッフが全てを介助することは、事故の予防には繋がるかもしれません。
しかし、出来る能力(食べる、歩く、座る)を使わずにいると、やはり身体の機能は落ちてしまいます。
集団生活の場なので、業務の効率化を考える事は必要ですが、それがご利用者の能力低下に繋がる対策になってはいけません。
「ありがとう」が返ってこない理由
頑張っているのに、
「ありがとう」
と言ってもらえない…。一生懸命だからこそ、辛く感じるかもしれません。
でもそれは、あなたの「やってあげている」という気持ちが前に出すぎているのかもしれません
「〇〇あげている」
という言葉には、善意や親切心が込められている一方で、無意識のうちに上下関係や自己犠牲の意識が含まれてしまうことがあります。
「自分がやってあげているのに…」
という思いが強くなると、感謝されないことへの不満やストレスにつながることがあります。
逆に、介護される側は「してもらってばかり」と感じ、自尊心を傷つけられることもあります。
本当に心に届く“やさしさ”は、自己満足ではなく、相手の立場に立って考えることから始まります。
介護の主役は“介護される人”
介護をしていると、つい「私がなんとかしなきゃ」と思いがちです。しかし、介護の主役はあくまで
“介護される人”
本人の希望、気持ち、できる力を大事にすること。それこそが、本当にあたたかく、誠実なやさしさではないでしょうか。
手を出すより、心を寄せる
やさしさは、手を出すことだけじゃありません。そっと心を寄せて、「あなたを信じてるよ」と見守ることも、立派な介護です。
そのやさしさは、相手のため?
それとも、自分が安心したいだけ?
もし迷ったときは、そんなふうに問いかけてみてください。
あなたの介護を“支配”から“支援”に変える第一歩になるはずです。
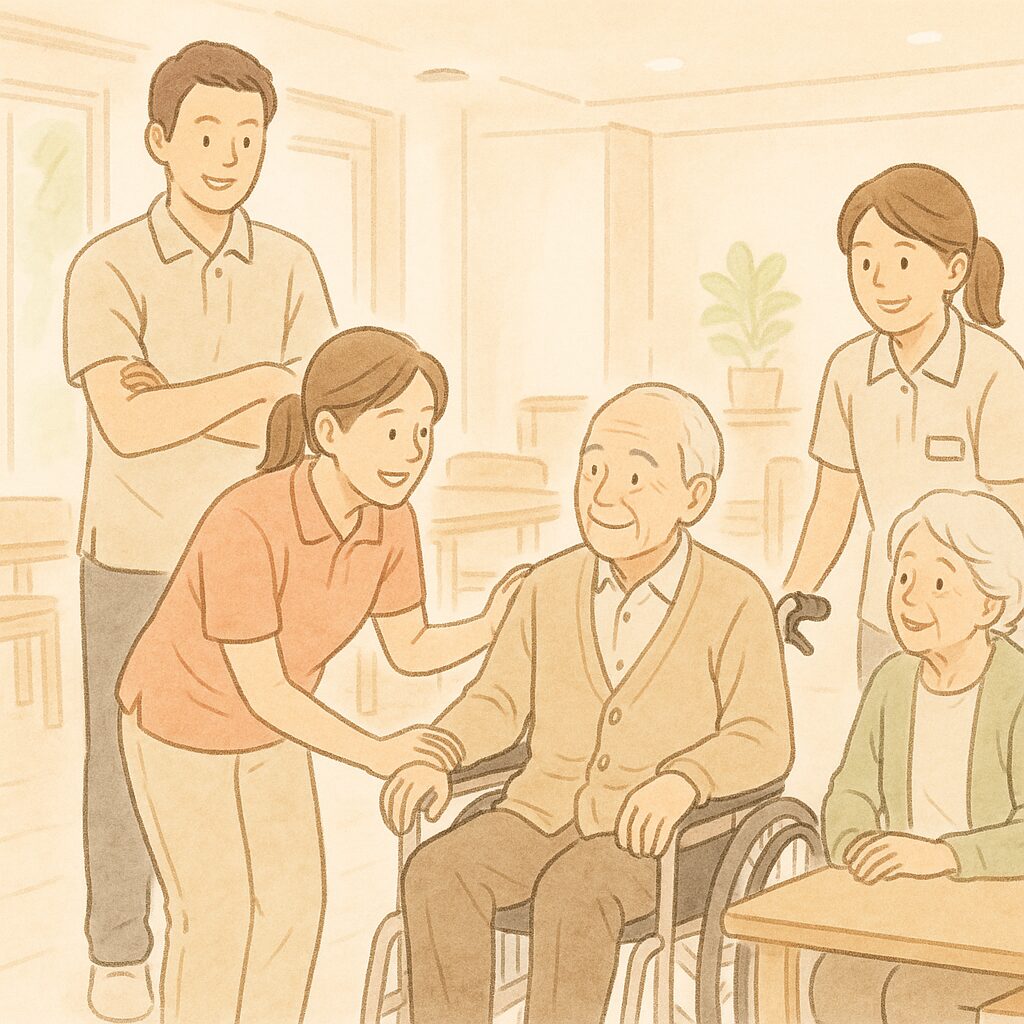

コメント